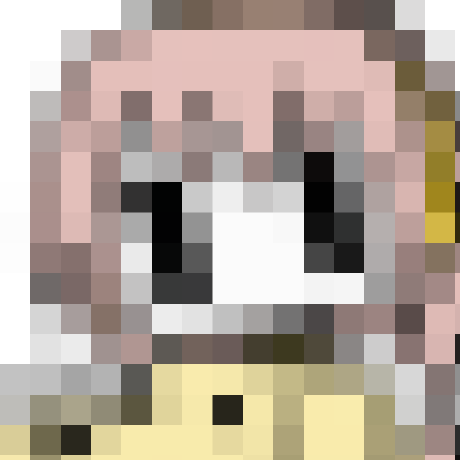Page 1
技術発信の信頼性を高める10のポイント
10 things to improve the credibility of your article
pixiv Inc.
USAMI Kenta
2022-08-25
公開日:
by USAMI Kenta@tadsan
にオンラインのYouTube Liveで開催された『今年こそは継続的にアウトプットすると決めた方向けに語る技術発信の取り組み方』で15分枠として発表しました。
技術発信の信頼性を高める10のポイント
10 things to improve the credibility of your article
pixiv Inc.
USAMI Kenta
2022-08-25
お前誰よ
今回のお題
プロポーザル
10という数は適当です
(任意の進数での10(n)ということにしてください)
個人的な遍歴
初めて技術記事(っぽいもの)
書いてから紙の雑誌に 寄稿するまで8年くらい
2000年代中旬からいろんなブログをつまみ食いして技術を学んだ
わからないなりに濫読したブログの(一見無駄な)知識が数年後に結びつく経験
初期の発信の原動力
誤情報への憤り
問題を解決したいときに 間違った情報が出てくる
とムカつく
自分の記事を 自分で読んで
ムカつかないように
誤情報への憤り
誤情報とは何か、読者にできること
間違った情報にしないための工夫
間違った情報にしないための工夫
信頼できる情報源
間違った情報にしないための工夫
固有名詞や言葉の使いかたに気を配る
コードが動くことをどう保証するか
初心者のおすすめの発信
書きたいネタがない…